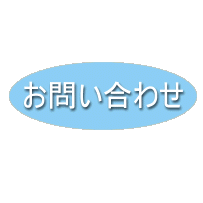|
|||
|
1週間程度 |
|
仮義眼を装用して調整 | |
|
|||
|
7日〜10日 |
|
||
|
|||
|
A.公費で義眼を製作する 「労災保険」や各種の「福祉法」により、公費で義眼を製作することができます。この場合には、当社へ来社する前にご本人が公費で義眼を製作する旨の手続きを先にする必要があります。これは、製作して2年以上経過すれば、手続きをすると取り替えるたびに支給されます。 |
| 種類 | 手続きの窓口 | 必要書類 | 支給金額 | 手続方法 | 条件 | |
| 1 | 労災保険 | 管轄の労働基準監督署 | 1.治療終了証明書 2.義肢等支給申請書 |
補装具基準額全額支給 | 治療が終了した時点で、「治療終了証明書」と備付けの「義肢等支給申請書」を提出する。後日渡される義肢等支給承認書と見積書を義眼製作施設へ持参する | |
| 2 | 生活保護法 | 住居地の福祉事務所 | 1.給付用紙意見書 | 補装具基準額全額支給 | 備付けの書類に必要事項を記入する。後日渡される治療材料券を義眼製作施設へ持参する。 | 医師が必要と認めた場合 |
| 3 | 障害者自立支援法 | 住居地の福祉事務所 (障害福祉課) |
1.医学的判定記録表 2.補装具交付(修理)申請書 |
補装具基準額内支給 (一割が基本的な自己負担分) |
備付けの書類に必要事項を記入し、身体障害者手帳を提示する。後日渡される補装具費支給券を義眼製作施設へ持参する。 | 同上 |
| 4 | 戦傷病者特別援護法 | 上記に準じる。 | 上記に準じる。 | 補装具基準額全額支給 | 上記に準じ「戦傷病者手帳」を提示する。 | 同上 |
|
B.自費で義眼を製作する 費用は標準的なもので10万円前後です。また無眼球の方は、原則的には義眼を製作した後に健康保険で義眼代金の一部の補助を受けることができます。これも、製作後2年以上経過すると、作り替える際同様に補助されます。 |
| 種類 | 手続きの窓口 | 必要書類 | 還付金額 | 手続方法 | 条件 | |||
| 1 | 社会保険 | 管轄の社会保険事務所 | 1.診断書又は意見書 2.装着証明書 3.業者の領収書 4.健康保険療養費支給申請書(用紙は社会保険事務所にあります) |
61,800円(目安) 特殊製作義眼(オーダーメイド)の場合 |
*1〜4までの書類 *印鑑 *振込銀行預金口座番号 を揃えて社会保険事務所の窓口で手続きをして下さい |
医師が必要と認めた場合 | ||
| 2 | 国民健康保険 | 住居地内市区町村役場の国民健康保険課窓口(職域国保の加入者は夫々の保険事務を取り扱っている所) | 1.診断書又は意見書 2.装着証明書 3.業者の領収書 4.国民健康保険療養費申請書(用紙は市区町村役場にあります) |
同上 | *1〜4までの書類 *印鑑 *振込銀行預金口座番号 を揃えて市区町村役場国民健康保険の窓口で手続きをして下さい |
同上 | ||
| 3 | 老人保健 | 住居地内市区町村役場の老人保険課窓口 | 1.診断書又は意見書 2.装着証明書 3.業者の領収書 4.老人健康保険療養費申請書(用紙は市区町村役場にあります) |
同上 | *1〜4までの書類 *印鑑 *振込銀行預金口座番号 を揃えて市区町村役場老人保健担当の窓口で手続きをして下さい(老人手帳持参のこと) |
同上 | ||
| 4 | 組合健康保険 | 管轄の組合保険事務所 | 社会保険に準じる。 (健康保険療養費支給申請書は職場の保険担当者からもらって下さい) |
同上 | 社会保険に準ずる。 | 同上 | ||
|
||||||||